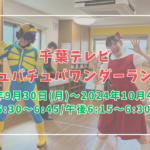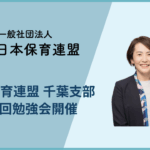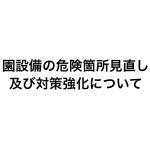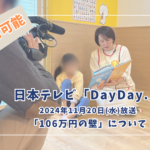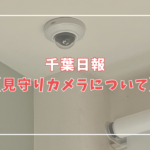こんにちは。統括園長の日向美奈子(ひゅうがみなこ)です。
厳しい暑さがやわらぎ、涼しさを感じる心地良い季節となってきました。
油断はできませんが、ようやく「熱中症」の危険性が低下していく時期となって内心ほっとしています。
キートスでは9月30日で全園水遊びを終了しました。9月末まで水遊びをする時代が来るとは。。。
さて、ついに【認定保育士履修証明プログラム】が開講し、先日第一期生となった方々とオリエンテーションに参加いたしました。
なんと!私も晴れて第一期生となりました。
これから、受講生の皆さんと共にまだまだ未知の「認定保育士」の認定を受けられるよう、仕事と学修に励んで参ります。
オリエンテーションで説明を受けて、ワクワクすると同時に、生半可な気持ちと行動では、到底認定を受けるに及ばないと実は内心ドキドキしているのも本音です。

【認定保育士履修プログラム】とは一体どんな目的をもったプログラムなのかというと
目的:保育士の方が、保育現場の課題を直接的に解決できる専門性を身につけるための教育プログラムです。
私が理事を務めている、「一般社団法人 日本保育連盟」が主体となり、保育士の専門性を高め、保育士のキャリアアップの道筋となり、相応の評価・対価を得られる仕組みを創るための制度です。
以前、第5回の保育のいま「保育士のキャリアアップについて」で、書かせていただきましたが、現在の園長・主任という肩書や経験年数だけで評価される仕組みから脱却し、「より専門的な知識を身に着けたい」「自身の能力を高めたい」「現場の課題を直接的に解決したい」という気持ちをもって学んだ保育士が、見合った待遇や社会からの評価を受けるための仕組みにすることが重要です。
私自身が日本保育連盟の理事として、制度を形骸化させないためにも第一期生として実際にプログラムを履修し、保育の仕事をしながら認定を受けようとチャレンジします。
履修は8科目で構成され、科目ごとにオンデマンド、Webライブ授業、レポート作成による合計60時間のプログラムとなっています。
最終的には論文書き、保育関連の学会誌に採録されて晴れて修了となります。修了者には学校教育法の規定に基づく履修証明書が交付されます。

① 障害児保育を支える理念―インクルーシブの理念と合理的配慮及び基礎的環境整備―
② 発達障害児の理解と援助
③ 心理教育アセスメント
④ 保護者に対する理解と援助―メンタルヘルスー
⑤ 指導計画および個別の指導計画作成
⑥ 小学校との連携・就学に向けてー多様性に対応する支援―
⑦ 子どもの保健:健康増進に向けた保育施設の役割
⑧ 認定保育士に向けて論文作成の基礎的ルール
星槎大学院の教員の方々から学び、論文指導を受けるという大学院並みのプログラムです。
スタートするに当たってハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
しかし、保育士資格をもっていたら誰でも容易に認定を受けられてしまうプログラムでは意味がないと私は考えています。ハードルが高いからこそ、認定保育士となった保育士の方の価値が見出されます。

とはいえ、スタートしたばかりのプログラムです。「難しそう」という想像だけで、保育士の方々には自分の可能性を狭めてほしくないと思っています。
日本保育連盟の保育士会員(個人)になれば、勤務先の保育園が会員でなくても、今は保育現場にいない方でも認定保育士資格の取得が可能です。
“誰かから言われたから”ではなく“自分が”専門性を高めて現場の課題解決をするスペシャリストになりたいから“という方にピッタリのプログラムだと思います。
スペシャリストにふさわしい評価・対価を得て、保育の仕事を生涯の仕事として自ら極めていく保育士が増えていくことこそ、どの保育園も追い続けている「保育の質の向上」の根拠となるのではないでしょうか。
保育現場の課題を【自分事として捉え解決するスペシャリスト】、必要とされ、評価されるべき存在を目指して、まず一歩踏み出してみませんか?
【プロフィール】

日本一バズる保育園を創った園長 日向 美奈子
“三刀流!保育園経営✕保育士✕現役大学院生“
【職歴】
2010年 株式会社ハイフライヤーズ設立
千葉市認可保育園7園/成田市認可保育園3園
役職:株式会社ハイフライヤーズ取締役社長 兼 保育運営本部 キートス統括園長
【学歴】
1997年 聖徳大学短期大学部保育科卒業
2020年 聖徳大学児童学部児童学科 児童心理コース編入 2022年 卒業
2022年 聖徳大学大学院 児童学研究科 児童学専攻 博士前期課程 入学
【所属】
一般社団法人日本保育連盟(理事/千葉支部長)
日本こども虐待防止学会
保育業界に関する事なら取材、撮影何でもお任せください。
現場に立つからこそ伝えられる情報をお答えします。